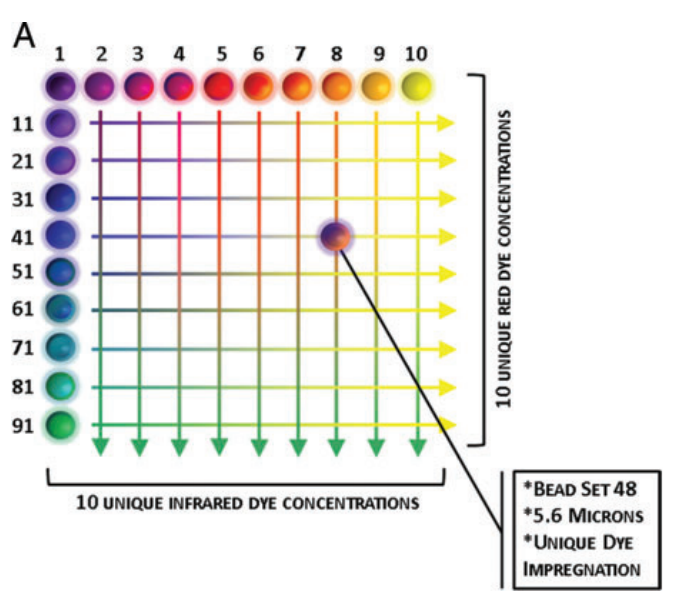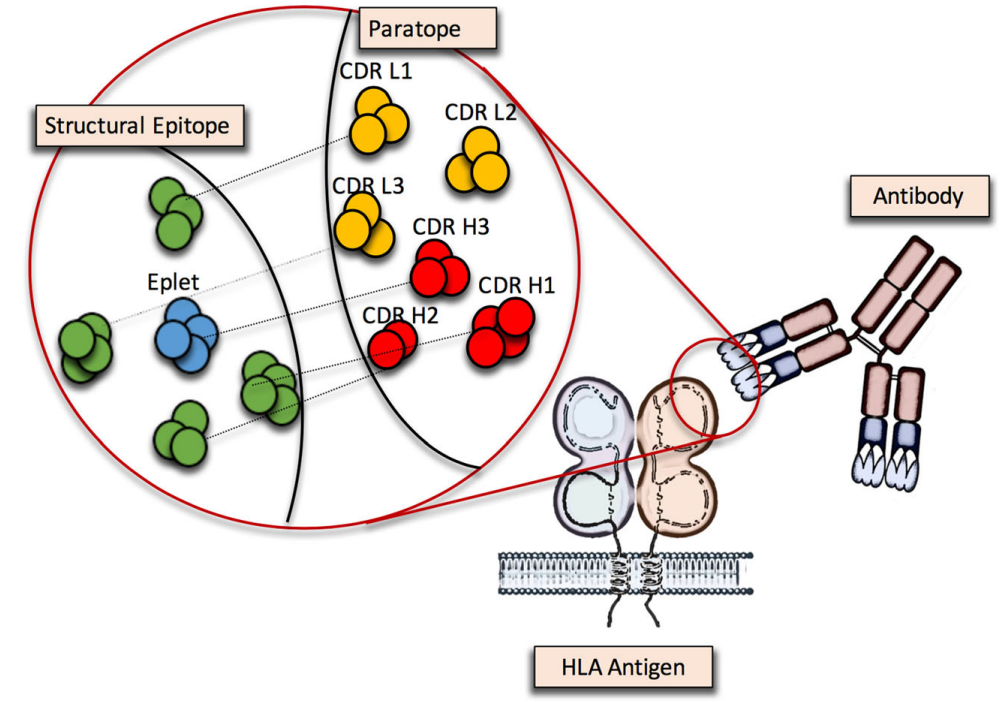先日紹介した"Sick Girl"を読んだ。移植医療の患者視点を、非常に深く正確に(理解できるように、あるいは理解できないことを理解できるように)これでもかと教えてくれる本だった。
一番の衝撃は、人生の意味についてのやりとりだった。もうこれ以上は無理であると絶望的に伝える患者に対して、主治医が「あなたの人生に意味を与えるものは何ですか?」と聞いた。
こんな質問をすることはまずない医師であったが、移植後10年以上の診療を経ての、絶望と怒りの果てに出た訴えに対するやり取りなので、そういう話にもなったのだろう。医師はまず仕事、そして家族を例に挙げる。
しかし、家族を置いて治療を放棄するのは無責任、といった批判でひっこめるほど単純な苦しみではない。たとえ非難されても仕方ない、自分のことは自分で決める、と思えるほど作者は追い詰められていた。
移植以来ずっと、作者にとって人生の意味は生きること(survival)だった。生きていなければ、その他のことなど何もない。だから、いつ拒絶するかもしれない、いつ感染やがんになるかもしれない、と思いながら必死に「患者」を生きてきた。
だから、主治医の質問に答えるには、移植をいったん脇に置いて、想像したこともないことを想像して、夢をみなければならない。そして、彼女から出た一言は:
"I'd like to write."
だった。
主治医は「じゃあ、書けばいい」と言う。書こうとしたが駄目だった、大学時代にクラスに何度か行ったが心臓病になり行けなかった、今からやろうとしても合うクラスがない、やっぱり無理だから薬(免疫抑制薬)を飲むのをやめる!
・・と、彼女は言い放った。
主治医はさらっと「免疫抑制薬を減らして、2週間後にレベルをチェックしましょう」、「それまでは毎週会いましょう」と言った。そして去り際に、「大学に確認して、個人教授のレッスンを組むこともできます、あなたのスケジュールに合わせられますよ」と言った。
この時のことを彼女は、I was caught up with olive branches(ノアの箱舟の例え)、と書いている。結果的に、そのおかげでこの本ができた。
二つ考察しなければならない。一つには、人生の意味について考えさせられた。生存、所属、愛情、・・自己実現と言ってしまえばそれまでだが、そこにこそドラマがある。単純に「次のレベルはこれかな?」とすくすくやっていけるほど、人生は甘くない。
もう一つは、医師に求められる落ち着きである。患者に「人生の意味は何ですか?」と聞くほど思い上がる気はないにしても、「治療をやめたい」という問いかけにどう向き合うかはどの医師も経験することだ。
この時主治医がとった対応は、患者が生きる意味を持っていて、でも心理的に溺れかけていて、「オリーブの枝を必要としていた」からこそ正解なのだろう。患者中心医療といっても、このようにリードすることが必要な場合もある。